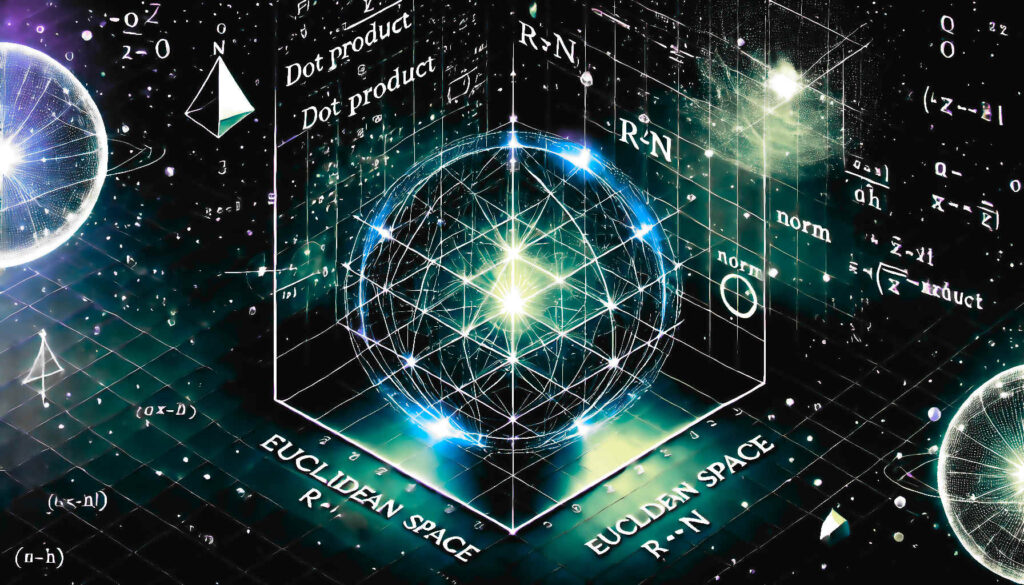ユークリッド空間 {\mathbb{R}^n}
この講義では、ユークリッド空間 \mathbb{R}^n、その代数的構造および距離に関する性質について探究します。ベクトル演算、内積、ノルム、ユークリッド距離など、幾何学および解析における基本的概念を学びます。明確な説明と直感的な例を通じて、多次元空間を数学的にどのようにモデル化するかを理解することができます。
学習目標:
この講義の終了時に、学生は以下ができるようになります:
- 定義する ユークリッド空間 \mathbb{R}^n とその基本的性質。
- 説明する \mathbb{R}^n のベクトル構造と基本演算による性質。
- 適用する 内積を用いてベクトル間の角度や射影を計算する。
- 証明する \mathbb{R}^n における内積の代数的および距離的性質。
- 利用する ユークリッドノルムによりベクトルの大きさを求める。
- 計算する \mathbb{R}^n における2点間のユークリッド距離とその幾何学的意味を分析する。
- 確認する コーシー・シュワルツの不等式や三角不等式のような基本的不等式の妥当性。
目次
ユークリッド空間 \mathbb{R}^n
内積
ノルムとユークリッド距離
結論
ベクトル空間 \mathbb{R}^n
この時点に到達する前に、\mathbb{R} の性質、あるいは平面 \mathbb{R}^2, や空間 \mathbb{R}^3 に慣れ親しんでいたことでしょう。 それらの概念はすべて、空間 \mathbb{R}^n を理解する上で有用です。まず何よりも、集合 \mathbb{R}^n = \{\vec{x} = (x_1, \cdots, x_n) | x_1, \cdots, x_n \in \mathbb{R}\} に通常のベクトルの加法とスカラー倍を備えたものはベクトル空間であり、ここでは \mathbb{R}^n の基本的な演算を詳しく見ていきましょう。
\mathbb{R}^n における基本演算
ベクトル \vec{x}=(x_1, \cdots, x_n), \vec{y}=(y_1, \cdots, y_n) が \mathbb{R}^n に属し、\alpha が任意の実数スカラーであるとき、以下に示すように、ベクトルの加算とスカラー倍の演算が定義されます:
ベクトルの加算: ベクトルの加算は次の関数によって記述されます:
\begin{array}{rcrl} +:& \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & (\vec{x},\vec{y}) & \longmapsto & \vec{x}+\vec{y} = (x_1+y_1, \cdots, x_n + y_n) \end{array}
スカラー倍: スカラー倍は次の関数によって記述されます:
\begin{array}{rcrl} ():& \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & (\alpha,\vec{x}) & \longmapsto & (\alpha\vec{x}) = (\alpha x_1, \cdots, \alpha x_n) \end{array}
\mathbb{R}^n のベクトル空間としての性質
上記で定義された演算を備えた \mathbb{R}^n は、ベクトル空間です。なぜなら、その加法およびスカラー倍の演算が以下に示す性質を満たしているからです:
まず、可換性と結合性の性質があります:
\vec{x} + \vec{y} = \vec{y} + \vec{x} \\ \vec{x} + (\vec{y} + \vec{z}) = (\vec{x} + \vec{y}) + \vec{z} \\ (\alpha \beta) \vec{x} = \alpha (\beta \vec{x}) = \beta (\alpha \vec{x}) = (\beta\alpha) \vec{x}
スカラーの加算はスカラー倍に関して分配され、ベクトル加算もスカラー倍に関して分配されます。すなわち、以下の等式が成り立ちます:
(\alpha + \beta) \vec{x} = \alpha\vec{x} + \beta\vec{x} \\ \alpha(\vec{x} + \vec{y}) = \alpha\vec{x} + \alpha\vec{y}
加法単位元 \vec{0}=(0,\cdots, 0) が存在し、次の性質を満たします:
\vec{x} + \vec{0} = \vec{x}
スカラー倍においては 乗法単位元 が存在し、
1 \vec{x} = \vec{x}
すべてのベクトル \vec{x}\in\mathbb{R}^n に対して、加法逆元 -\vec{x} が存在し、次の性質を満たします:
\vec{x} + -\vec{x} = \vec{0}
内積(スカラー積)
ベクトル空間として \mathbb{R}^n の構造を観察すると、そこにはベクトル同士の積が存在しないことがわかります。つまり、通常の実数のようにベクトル同士を「掛ける」ことはできません。しかし、ベクトル間に定義可能な演算があり、その一つが 内積(スカラー積) として知られています。
内積(スカラー積)とスカラー倍を混同してはなりません。 前者は2つのベクトルの積であり、結果はスカラー(実数)になります。後者はスカラーとベクトルの積であり、結果はベクトルです。ここでは \mathbb{R}^n に属する2つのベクトル \vec{x}=(x_1, \cdots, x_n) および \vec{y}=(y_1, \cdots, y_n) を考えます。これらを用いて、\vec{x} と \vec{y} の内積 \vec{x}\cdot\vec{y} は次の式によって定義されます:
\vec{x}\cdot\vec{y} =\displaystyle \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1y_1 + \cdots x_ny_n
ベクトル空間 \mathbb{R}^n における内積の表現にはさまざまな方法があります。一つは上記の式であり、もう一つは \mathbb{R}^n の基底とアインシュタインの縮約記法を用いる方法です:\{\hat{e}_i\}_{i=\overline{1,n}} を \mathbb{R}^n の基底(通常は標準基底)とすると、ベクトル \vec{x} と \vec{y} は次のように表されます:
\vec{x}=\displaystyle\sum_{i=1}^n x_i\hat{e}_i = x_1\hat{e}_1 + \cdots x_n\hat{e}_n
\vec{y}=\displaystyle\sum_{i=1}^n y_i\hat{e}_i = y_1\hat{e}_1 + \cdots y_n\hat{e}_n
ここでは、ベクトルの係数 x_i および y_i が空間の基底に対するものであることが明示されています。
アインシュタインの和記法
アインシュタインの和記法 は、ベクトルの表記全般および特に内積の表現を簡潔にするための方法です。前の2つの式を見てみると、添字 i がベクトルの係数と基底ベクトルの両方に現れています。アインシュタインによれば、添字が繰り返されている場合、それは和を意味しているとみなせるため、次のように書くことができます:
\vec{x}= x_i\hat{e}_i
\vec{y}= y_i\hat{e}_i
この記法を用いると、内積は次のように表現されます:
\vec{x}\cdot\vec{y} = x_i\hat{e}_i \cdot y_i\hat{e}_i = x_iy_i \underbrace{(\hat{e}_i \cdot \hat{e}_i)}_{=1} = x_iy_i
この最後の等式では、標準基底を用いていることが仮定されています。
内積に関する他の記法
ベクトルおよびその演算の記法は文脈によって異なることが多く、この節の冒頭で用いたものは、微積分の文脈で最もよく見られる一般的な形式です。一方、線形代数学ではベクトルと共ベクトルを区別して記述することもあります:
ここで「ベクトル」とは「列ベクトル」を意味し、行列表現では次のように書かれます:
\alpha^i = \left( \begin{array}{c}\alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{array} \right)
一方、「共ベクトル」とは「行ベクトル」を意味し、行列表現では次のように書かれます:
\beta_i = \left( \beta_1 \; \cdots \; \beta_n \right)
このようにして、2つのベクトル \vec{x}=(x_1,\cdots,x_n) および \vec{y}=(y_1,\cdots,y_n) の内積は、「共ベクトル」x_i とベクトル y^i の行列積として解釈され、次のような実数が得られます:
\left( x_1 \; \cdots \; x_n \right) \left( \begin{array}{c}y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{array} \right) = x_iy^i
この最後の等式にもアインシュタインの和記法が再び登場します。添字の繰り返しが、結果が和であることを示しています。
ベクトルと共ベクトルを添字と上付き記号で区別する記法は「共変記法」または「テンソル記法」として知られており、特殊相対性理論や一般相対性理論の研究において広く用いられています。この記法は、今見てきた内容をさらに一般化した概念であるテンソルを扱う際にも便利です。このテンソルの概念については、別の機会に詳しく取り上げることになります。量子力学のような他の分野では、Bra–Ket 記法が好まれ、次のように表されます:
\left< x \right| =\left( x_1 \; \cdots \; x_n \right) \\ \\ \left|y\right> = \left( \begin{array}{c}y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{array} \right)
このとき、内積(スカラー積)は次のように表されます:\left<x|y\right>.
内積の性質
内積の定義からは、将来的に非常に重要となる多くの性質を導くことができます。
内積を用いて、次のような関数 \tilde{\omega}(\vec{x})=\vec{\omega} \cdot \vec{x} = \omega_i x^i を定義すると、この \tilde{\omega} という関数は線形関数のすべての性質を満たすことがわかります。実際、次の性質が簡単に証明できます:
\begin{array}{rl} \tilde{\omega}(\alpha \vec{x} + \beta\vec{y}) = \alpha \tilde{\omega}(\vec{x}) + \beta\tilde{\omega}(\vec{y}) \end{array}
したがって、このように内積から定義される \tilde{\omega} のような対象は 線形汎関数(functional lineal)と呼ばれます。すでに知っているように、\vec{x} は ベクトル空間 \mathbb{R}^n の要素であり、\tilde{\omega} は \mathbb{R}^n の 双対空間 の要素です。
このことから、内積と線形関数の間には密接な関係があることがわかります。実際、内積の重要な性質をまとめた表現として以下のように述べることができます:「内積は双線形・対称・正定値・非退化な形式である」。それぞれの意味を見ていきましょう:
内積が双線形形式である というのは、\vec{x},\vec{y} および \vec{z} が \mathbb{R}^n のベクトルであり、\alpha,\beta \in \mathbb{R} のとき、次の2つの等式が成り立つということです:
\begin{array}{rl} \vec{x}\cdot(\alpha \vec{y} + \beta\vec{z}) = \alpha (\vec{x}\cdot\vec{y}) + \beta(\vec{x}\cdot\vec{z}) \\ \\ (\alpha \vec{x} + \beta\vec{y})\cdot\vec{z} = \alpha (\vec{x} \cdot \vec{z}) + \beta(\vec{y}\cdot\vec{z}) \end{array}
内積は対称的です。なぜなら:
\forall(\vec{x},\vec{y}\in\mathbb{R}^n)(\vec{x}\cdot\vec{y} = \vec{y}\cdot\vec{x})
また、正定値です。なぜなら:
(\forall\vec{x}\in\mathbb{R}^n)(\vec{x}\cdot\vec{x} \geq 0)
さらに、非退化性(ノンデジェネレート)を持ちます。なぜなら:
\vec{x}\cdot\vec{x} = 0 \leftrightarrow \vec{x}=\vec{0}
ノルムとユークリッド距離
ノルムとは、ベクトルの大きさ(長さ)を測る方法です。ノルムを備えたベクトル空間は、ノルム空間(Normed Vector Space)と呼ばれます。\vec{x},\vec{y}\in\mathbb{R}^n および \lambda\in\mathbb{R} のとき、関数 Norm( . ) が以下の性質を満たせば、それはノルムと呼ばれます:
- Norm(\vec{x})\geq 0(非負性)
- Norm(\vec{x}) = 0 \leftrightarrow \vec{x}=\vec{0}(零ベクトルとの同値性)
- Norm(\lambda\vec{x}) = |\lambda| Norm(\vec{x})(スカラー倍に対する斉次性)
- Norm(\vec{x} + \vec{y}) \leq Norm(\vec{x}) + Norm(\vec{y})(三角不等式)
内積の重要な側面の一つは、それが直感的に理解できる2点間の距離という概念を数学的に定義するために非常に有用であるという点です。任意の \vec{x}\in\mathbb{R}^n に対して、ユークリッドノルム \|\vec{x}\| が次の式で定義されます:
\|\vec{x}\| = \sqrt{\vec{x}\cdot\vec{x}}
このことから、ユークリッドノルムは内積によって誘導されるノルムであると言えます。
距離(または距離関数、メトリック)とは、「集合内の2要素間の隔たり(距離)」を定量化する関数のことです。\vec{x}, \vec{y}, \vec{z}\in\mathbb{R}^n および \lambda\in\mathbb{R} に対して、関数 Dist( . ) が以下の性質を満たせば、それは距離(メトリック)と呼ばれます:
- Dist(\vec{x},\vec{y})=0 \leftrightarrow \vec{x}=\vec{y}(識別性)
- Dist(\vec{x},\vec{y})=Dist(\vec{y},\vec{x})\geq 0(対称性と非負性)
- Dist(\vec{x},\vec{z})\leq Dist(\vec{x},\vec{y}) + Dist(\vec{y},\vec{z})(三角不等式)
最後の性質は三角不等式として知られており、これが成り立たない場合、関数 Dist(.) は「擬距離関数」あるいは「擬メトリック」と呼ばれることになります。距離を備えたベクトル空間は、距離空間(メトリック空間)と呼ばれます。
ユークリッドノルムに基づいて、ユークリッド距離が2つのベクトル間に定義されます。\vec{x},\vec{y}\in\mathbb{R}^n という2つのベクトルがあるとき、これらの間のユークリッド距離 dist_e(\vec{x},\vec{y}) は次の式で与えられます:
dist_e(\vec{x},\vec{y}) = \|\vec{x} - \vec{y}\|
ここで \vec{x}=(x_1,\cdots,x_n) および \vec{y}=(y_1,\cdots, y_n) のとき、内積とノルムの性質から次のように簡単に導けます:
dist_e(\vec{x},\vec{y}) = \sqrt{\displaystyle \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}
ベクトル空間 \mathbb{R}^n にユークリッド距離を導入することで、ユークリッド空間 が得られます。
このことから、ユークリッド空間の距離(メトリック)は、ユークリッドノルムによって誘導されるメトリックであると言われます。
ユークリッドノルムの性質
本講義では特にユークリッド空間を対象としているため、ユークリッドノルムの性質を確認しておくことは有益です。
コーシー・シュワルツの不等式
もし \vec{x},\vec{y}\in\mathbb{R}^n ならば、次の性質が成り立ちます:
|\vec{x}\cdot\vec{y}|\leq \|\vec{x}\|\|\vec{y}\|
証明:
\lambda = (\vec{x}\cdot\vec{y})/\|\vec{y}\|^2 とおくと、次のようになります:
\begin{array}{rl} 0\leq \|\vec{x} - \lambda \vec{y}\|^2 &= (\vec{x} - \lambda\vec{y}) \cdot (\vec{x} - \lambda\vec{y}) \\ \\ \displaystyle &= \vec{x}\cdot\vec{x} - \lambda\vec{x}\cdot\vec{y} + \lambda\vec{y}\cdot\vec{x} + \lambda^2(\vec{y}\cdot\vec{y})\\ \\ &= \|\vec{x}\|^2 - 2\lambda(\vec{x}\cdot\vec{y}) + \lambda^2 \|\vec{y}\|^2 \\ \\ \displaystyle &= \|\vec{x}\|^2 - 2\left(\frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{\|\vec{y}\|^2}\right)(\vec{x}\cdot\vec{y}) + \left(\frac{\vec{x}\cdot\vec{y}}{{\|\vec{y}\|^2}}\right)^2 {\|\vec{y}\|^2}\\ \\ \displaystyle &= \|\vec{x}\|^2 - 2\left(\frac{(\vec{x}\cdot\vec{y})^2}{\|\vec{y}\|^2}\right) + \frac{\left(\vec{x}\cdot\vec{y}\right)^2}{\|\vec{y}\|^2}\\ \\ &= \|\vec{x}\|^2 - \frac{\left(\vec{x}\cdot\vec{y}\right)^2}{\|\vec{y}\|^2} \end{array}
したがって、次のように言えます:
\displaystyle 0 \leq \|\vec{x}\|^2 - \frac{\left(\vec{x}\cdot\vec{y}\right)^2}{\|\vec{y}\|^2}
したがって:
\left(\vec{x}\cdot\vec{y}\right)^2 \leq \|\vec{x}\|^2 \|\vec{y}\|^2
最後に平方根をとると、次のように示されました:
|\vec{x}\cdot\vec{y}| \leq \|\vec{x}\| \|\vec{y}\| ⬛
三角不等式
ベクトル \vec{x},\vec{y}\in\mathbb{R}^n に対して、次の関係が成り立ちます:
\|\vec{x} + \vec{y}\| \leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|
証明:
まず次のことに注目します:
\begin{array}{rl} \|\vec{x} + \vec{y}\|^2 &= (\vec{x} + \vec{y})\cdot(\vec{x} + \vec{y}) \\ \\ &=\|\vec{x}\|^2 + 2(\vec{x}\cdot\vec{y}) + \|\vec{y}\|^2 \end{array}
次の不等式が成り立つので:
\vec{x}\cdot\vec{y}\leq |\vec{x}\cdot\vec{y}| \leq \|\vec{x}\|\vec{y}\|
次のように書けます:
\begin{array}{rl} \|\vec{x} + \vec{y}\|^2 &\leq \|\vec{x}\|^2 + 2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\| + \|\vec{y}\|^2 \\ \\ &\leq \left(\|\vec{x}\| + \|\vec{y}\| \right)^2 \end{array}
最後に平方根を取れば、次のように証明されます:
\|\vec{x} + \vec{y}\|\leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\| ⬛
結論
この講義を通じて、ユークリッド空間 \mathbb{R}^n の基本的性質について学びました。まず、ベクトルの加算や内積といった基本的な演算を定義することで、この空間がベクトル空間であることを確認しました。
続いて、内積の概念とその \mathbb{R}^n における幾何学的意味を掘り下げ、行列表現や線形関数との関係にも注目しました。
さらに、ユークリッドノルムとそれによって誘導される距離について考察し、これらの道具が空間内の長さや距離を定量的に扱うのに有効であることを確認しました。また、以下のような基本的な性質を確認しました:
|\vec{x}\cdot\vec{y}| \leq \|\vec{x}\| \|\vec{y}\|
(コーシー・シュワルツの不等式)および:
\|\vec{x} + \vec{y}\|\leq \|\vec{x}\| + \|\vec{y}\|
(三角不等式)これらは、解析や幾何学のより高度な理論を展開するうえで重要な基礎となります。